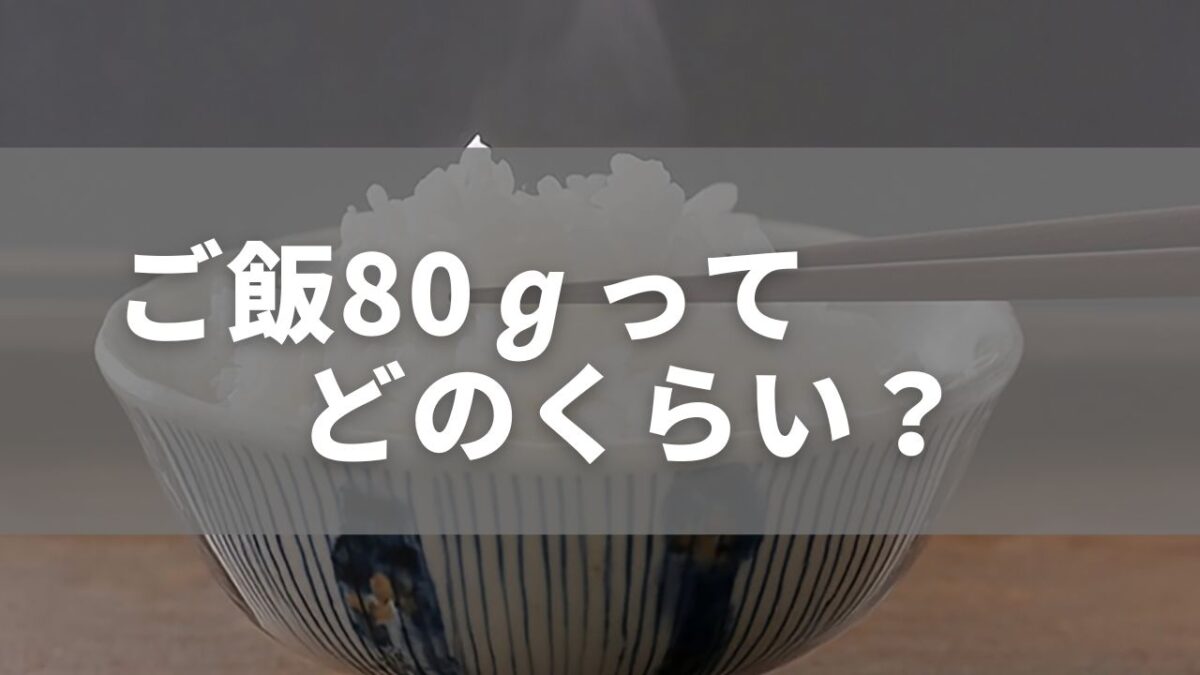「ご飯80gってどのくらい?」と思ったことはありませんか。
お茶碗にどれくらい盛ればいいのか、実際に見たことがないとイメージしにくいですよね。
この記事では、ご飯80gの簡単な量り方や見た目の目安、毎日続けやすい工夫などをわかりやすく紹介します。
スケールを使わなくても量れる方法や、お茶碗の目安、小分け保存のコツなど、すぐに実践できるアイデアばかり。
「食べすぎを防ぎたい」「無理なくご飯量を調整したい」と思っている人にぴったりの内容です。
 はるさん
はるさん専門的な知識がなくても大丈夫ですよ~。
今日からすぐに使える身近なテクニックで、無理なく「ちょうどいいご飯量」を習慣にしていきましょう。
ご飯80gってどのくらい?実際の見た目とお茶碗の量をチェック
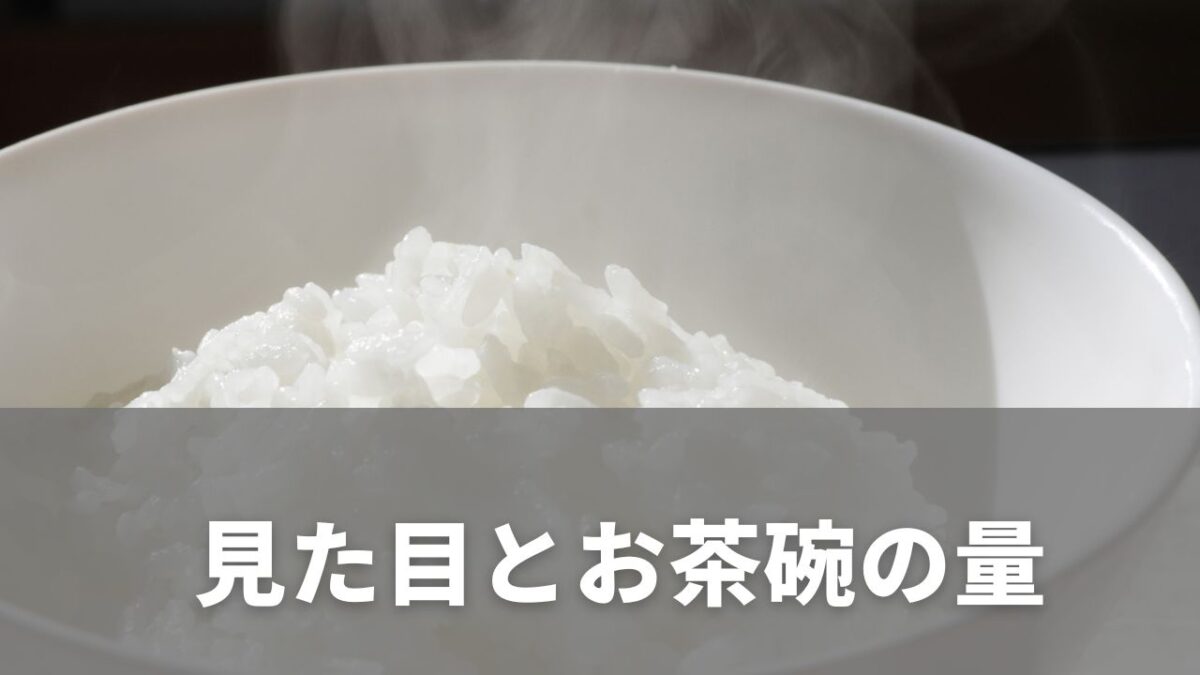
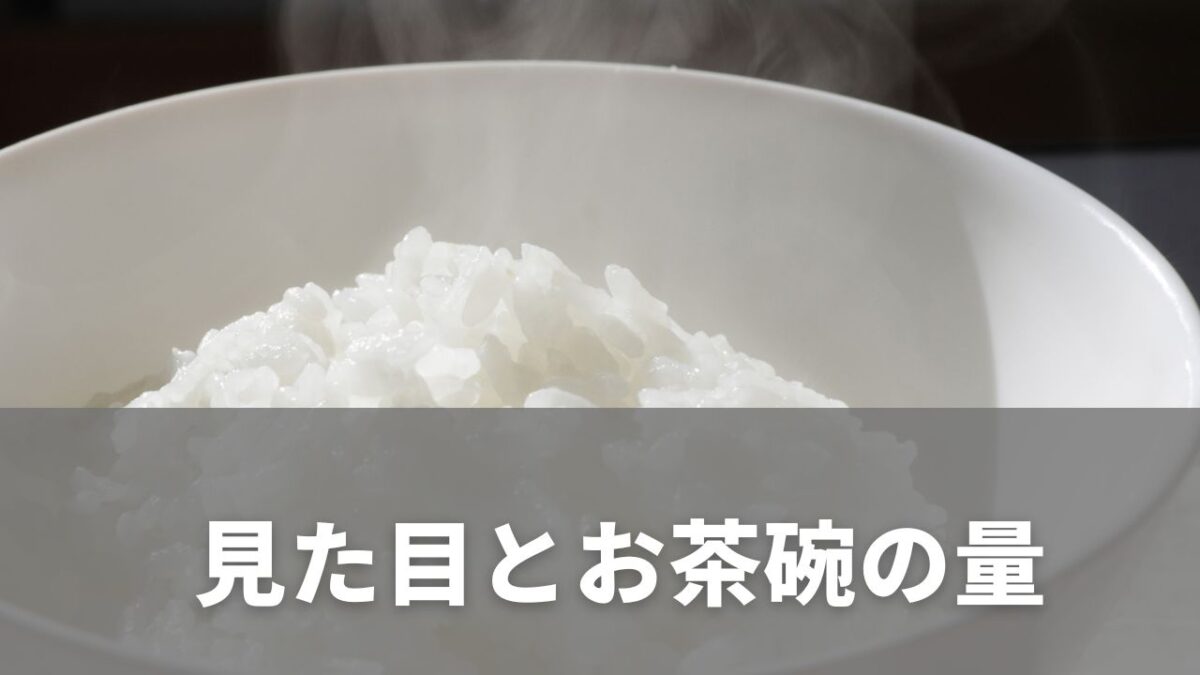
「ご飯80g」と聞いても、いまいちピンとこない人も多いかもしれません。
この章では、お茶碗に盛ったときの見た目や、一般的なご飯の量と比較しながら、感覚的にイメージできるように解説します。
お茶碗に盛ったときのご飯80gの目安
一般的なお茶碗一杯は、だいたい150g前後のご飯が入ります。
つまり、80gはお茶碗の半分より少し多いくらいの量になります。
見た目としては「軽く盛った」印象で、山ができない平らな感じです。
最初は「少ないな」と思うかもしれませんが、よく噛んでゆっくり食べると満足感を得やすくなります。
| ご飯の量 | 重さの目安 | お茶碗での見た目 |
|---|---|---|
| 半分盛り | 約75g | お茶碗の半分くらい |
| 小盛り | 約100g | お茶碗6〜7割ほど |
| 普通盛り | 約150g | お茶碗1杯分 |
150gの普通盛りと比較してみるとどのくらい違う?
150gのご飯と比べると、80gは約半分の量です。
見た目にもかなり違いがあり、同じお茶碗でもスカスカに見えることがあります。
ですが、他のおかずをしっかり組み合わせれば、少ない量でも満足感を得られます。
視覚で覚える「ご飯80g感覚」のコツ
毎回スケールで測るのは面倒ですよね。
そこでおすすめなのが、「自分の茶碗の半分+ほんの少し」という目安を覚えること。
この感覚を繰り返し意識していくと、自然と80g前後を盛れるようになります。
ご飯80gを簡単に量る方法3選(スケールなしでもOK)


「正確に80gを測るのって大変そう」と思う方も多いですが、コツをつかめば意外と簡単です。
ここでは、特別な道具を使わなくてもできるシンプルな方法を3つ紹介します。
お茶碗半分+αでおおよそ80gに
お茶碗に軽く半分ご飯を盛って、そこにスプーン1〜2杯だけ足すと、だいたい80g前後になります。
慣れてくると、見た目だけでおおよその量を判断できるようになります。
忙しい朝やお弁当作りのときにも便利な方法です。
| 方法 | 目安量 | ポイント |
|---|---|---|
| お茶碗半分+スプーン2杯 | 約80g | 最も手軽で続けやすい |
| おにぎり1個分 | 約80g | 視覚的に覚えやすい |
| タッパー1個分(小型) | 約80g | 冷凍保存にも便利 |
計量しゃもじを使えば一目でわかる
最近は、ご飯をすくうだけで重さがわかる計量しゃもじも販売されています。
80gを測る目安線が付いているタイプもあり、忙しいときにもサッと使えます。
1000円前後で手に入るため、手軽にご飯量を管理したい人にぴったりです。
炊飯器で炊いたご飯をざっくり分ける裏ワザ
たとえば2合(約660g)のご飯を炊いて、8等分に分ければ、1つあたり約82gになります。
この方法なら、スケールがなくても均等に分けられます。
冷凍保存しておけば、毎回測る手間も省けて一石二鳥です。
「ざっくり8等分」でちょうどいいと覚えておくと便利ですよ。
ご飯80gを毎日続けやすくする工夫


ご飯の量を意識しても、毎日続けるのはなかなか大変ですよね。
ここでは、手間をかけずに「ご飯80g」を自然に続けられるコツを紹介します。
冷凍保存なら忙しい朝も時短できる
炊きたてのご飯を80gずつラップで包んで冷凍しておくと、いつでもすぐ使えて便利です。
週末にまとめて冷凍しておけば、平日の食事準備がぐっと楽になります。
ラップで包む前にしっかり粗熱を取ることで、風味が保たれやすくなります。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 炊きたてご飯を80gずつ分ける | 温かいうちに分けると扱いやすい |
| 粗熱を取ってからラップで包む | 食感が損なわれにくい |
| 平らにして冷凍庫へ | 解凍時にムラなく温まる |
忙しい朝でも電子レンジで温めるだけでOKです。
「80g×数個」を冷凍庫に常備しておくと、時短にも食べすぎ防止にもなるのでおすすめです。
タッパーや小分け容器で「80g定番化」
100円ショップなどで手に入る小型タッパーを使えば、「この容器=80g」と決めておくことができます。
一度量っておけば、次からはスケールを使わなくてもラクに管理できます。
そのまま電子レンジで温められるタイプなら、洗い物も減らせて一石二鳥です。
| 容器タイプ | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| 小型タッパー(丸型) | おにぎりサイズで扱いやすい | 冷凍→電子レンジが簡単 |
| 小型タッパー(角型) | 収納しやすく重ねやすい | 冷凍庫内がすっきり整理できる |
冷凍庫の中に同じサイズの容器が並ぶと、見た目もスッキリして気分が上がります。
視覚的にもわかりやすく、習慣化しやすいのがこの方法の強みです。
おにぎり1個=ご飯80gと覚えておこう
コンビニのおにぎりはおよそ100〜120gですが、小さめに握れば約80gになります。
このサイズを目安にしておくと、出先での軽食やお弁当の量調整にも使えますよ^^
「おにぎり1個=ご飯80g」と覚えておくと、外食や間食のときにも役立ちます。
小腹が空いたときは80gおにぎりを1個だけ食べる、というルールを作るのもおすすめです。
ご飯の量と重さの早見表(見た目でわかる一覧)


「お茶碗の何分目くらいが80g?」と迷うときに便利なのが、見た目でわかる早見表です。
ご飯の重さとお茶碗の盛り具合をセットで覚えておくと、感覚的に量を調整できるようになります。
ご飯の量別・お茶碗の見た目比較
以下の表は、ご飯の重さごとに見た目とおすすめのシーンをまとめたものです。
80gがどんな量かを把握するうえでの参考にしてみてください。
| ご飯の量 | 重さ | お茶碗の見た目 | おすすめの場面 |
|---|---|---|---|
| 半分盛り | 約75g | お茶碗の半分くらい | 軽めの朝食に |
| 80g | 約80g | お茶碗の半分+少し | 普段の食事量を減らしたいとき |
| 小盛り | 約100g | お茶碗の6割ほど | ランチや軽い夕食に |
| 普通盛り | 約150g | お茶碗1杯分 | 標準的な食事に |
| 大盛り | 約200g | お茶碗山盛り | がっつり食べたいとき |
用途別におすすめのご飯量を紹介
ライフスタイルや活動量に応じて、ご飯の量を変えるのも一つの方法です。
以下のように目安を作っておくと、無理なく続けやすくなります。
| シーン | ご飯の量 | ポイント |
|---|---|---|
| 朝食 | 約80g | 軽めでエネルギー補給に |
| 昼食 | 約100〜120g | 活動量に合わせて調整 |
| 夕食 | 約80g | 控えめにして寝る前の負担を減らす |
数字で覚えるより「見た目」で覚えるほうが続けやすいので、自分のお茶碗で確認してみるのがおすすめです。
まとめ:ご飯80gを習慣にして、無理なく食事管理を続けよう
ここまで「ご飯80gはどのくらい?」という疑問から、量り方や続けやすい工夫まで紹介してきました。
最後に、続けるためのポイントをもう一度整理しておきましょう。
無理せず「量を意識する」だけでOK
ご飯80gを続けるコツは、完璧を目指さず、まず「おおよそこのくらい」と感覚をつかむことです。
毎回きっちり測らなくても、見た目で量を覚えれば十分です。
「お茶碗半分+少し」や「小さめおにぎり1個」といった自分なりの目安を持っておくと、ストレスなく続けられます。
| 意識のポイント | できること |
|---|---|
| 完璧を求めない | ざっくり感覚でOK |
| 目で覚える | お茶碗の見た目で調整 |
| 習慣化する | 同じ容器や量り方を使う |
続けることで自然とバランスが整う
ご飯の量を意識していくと、自然と食事全体のバランスも整いやすくなります。
無理に制限するより、続けられる工夫を積み重ねるほうが結果につながります。
「食べすぎない感覚」を身につけることが、日常の中での一番のポイントです。



今日から、まずは「ご飯80g」を意識してみましょう。
続けるうちに、自分にぴったりの量が自然とわかってくるはずですよ。